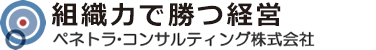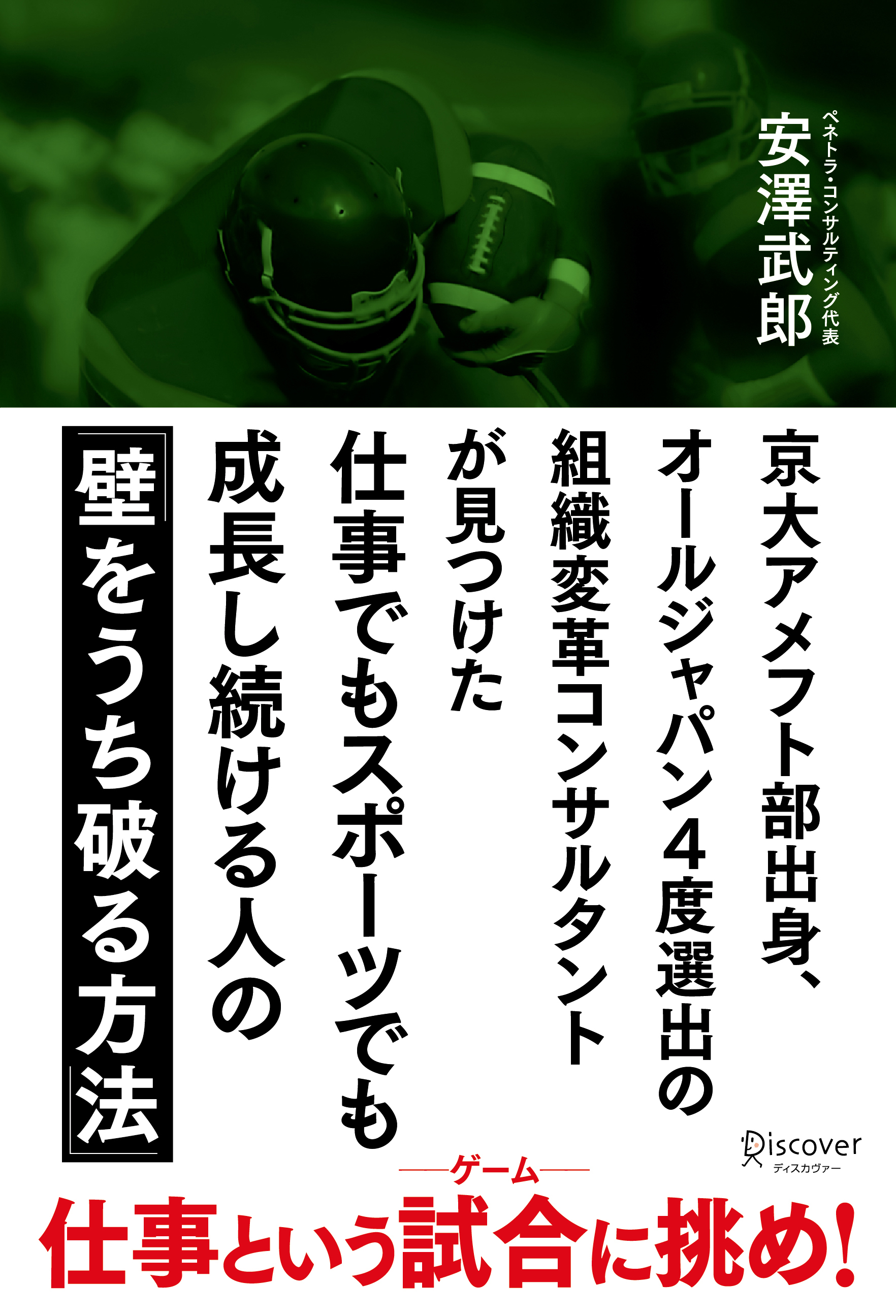組織の問題解決力を高める(1/2)
企業の発展段階における構造的な問題
企業には成長段階があります。
ハーバードのラリー・E・グレイナーは、その発展段階を5段階に分類をし、
適切なマネジメント行動を取るためのヒントを提供しました(1972年)。
どのような組織も人間の性には逆らえず、
構造的な問題として、各段階で問題が生じます。
ある段階での解決策が次の発展段階での問題を引き起こすのです。
例えば、創業者が自分だけでマネジメントをできなくなってきたと感じ、
有能なマネジャーに「指揮」をさせます。
しかし、有能なマネジャーにイニシアティブを握られている下位のマネジャーは、
現場に精通している自分たちの判断を尊重すべきと考えるようになります。
そのようにして「自主」に対する要求が高まると、
組織内で「委譲」が進められるようになります。
「委譲」が進むと、セクショナリズムは必ず発生します。
各所で自分のセクションを牛耳ようとする輩が出るに至って、
トップは現場の統制力を取り戻そうとします。
このような流れは、現体制を築いた人間の資質によるものではなく、構造的な問題です。
多くの人は、この変化を俯瞰的に捉えることができず、現体制の批判を行います。
「誰か」の責任問題になり、建設的な議論ができていない企業も目にします。
「人」を責めるのではなく、広い視野で問題を捉え、
次の発展段階のために必要な課題解決に取り組んでいくことが大切なのです。
硬直化した組織や本社と現場の信頼関係が失われた組織では、
現場の問題は共有されにくくなります。
現場の立場で考えれば、
「自分たちの方がよくわかっている」
「本社に相談をしても無駄だ」などと、
官僚的なレポーティングシステムをこなすことが目的になります。
一方で、本社側も現場の問題を解決する力を失っていき、
手続きの話しかしなくなります。
これは構造的な問題として生じるものですが、
問題解決の議論がまともになされないと「問題解決のスキル」も失われてしまいます。
逆に、この状況を脱する上で役立つのが「問題解決スキル」でもあります。
本社が現場との対話を深め信頼関係を再生していくことができるように、
現場が困っていることを本社に相談しやすくするために、問題解決のコツを考えてみましょう。
企業体で問題が解決される3つの段階
まず初めに、企業体で問題が解決される3つの段階から見ていきましょう。
「①個々で問題解決をする」
「②現場チームで問題解決をする」
「③経営チームと現場チームが協働で問題解決をする」と、
問題の難易度に応じて巻き込むべき範囲は変わってきます。
今まで解決できていなかった問題が解決するということは、
自分の問題解決力が高まったか、
今まで巻き込めなかった人を問題解決に参加させることができた
かのどちらかではないかと思います。
逆に、「問題が解決できなかった」というケースを振り返ると、
「こういう知識やスキルがあったらよかった」
「こういう点に気がついていれば良かった」
「この人に相談をしておけば、解決できたかもしれない」ということがあるでしょう。
「現場(中間)管理職」の立場で考えれば、
「①部下に任せて解決させること」
「②自分も参加をして解決すべきこと」
「③経営チームまで巻き込んで解決すべきこと」の3種類になります。
いずれにせよ、問題が解決できるかどうかは、
個々の問題解決力を高めるか、必要な人を問題解決に参加させるか、で決まってきます。
直近の課題解決を振り返ると何が言えるでしょうか?
今後より課題解決を進める上で、
改善すべきは①でしょうか?②でしょうか?③でしょうか?
それとも、①②③を見極める判断基準でしょうか?
問題解決の基本
問題解決の最大のコツは、「解決する」と決める(先送りをしている人はいつまでも解決できません)ことですが、
ここでは、問題解決のもう一つの基本を共有したいと思います。
それは「分解をする」ということです。
大きな問題も取り扱えるレベルに小さく分解をすると解決できるということです。
例えば、「直近の課題解決について振り返りをしましょう」という時と、
上記のように場合分けをして、「①②③それぞれ振り返りましょう」という時では、
どちらが具体的に考えられるでしょうか?
おそらく後者ではないかと思います。
このように、問題を切り分けて解決のツボを特定することが問題解決の基本であります。
例えば、「きく力を高めよう」という取り組みをする際に、
「相手の話をしっかり聞く」という視点しかなかったとしたら、
耳をそばだてることしかしないかもしれません。
しかし、「聞く(hear)」「訊く(ask)」「聴く(Listen)」の違い
を区別できるようになり、
自分は「訊く」があまりできていないな、
などと成長余地を具体的に特定できるようになると、
質問力や話の背景を捉える力は高まっていくでしょう。
他にも、「部下のモチベーションを上げる」という切り口を考えるときに、
「must(すべき)」「will(したい)」「can(できそう)」という切り口を使うと、
部下のどこを支援すれば良いか考えやすいのではないでしょうか?
いくら「やりたいこと」を部下にヒアリングをしたとしても、
その部下に「できること」が少なければ、多くの「やりたいこと」は出てきません。
部下に意欲がないのではなく、
「できそう」に思えないので「やりたい」とも思えないのです。
車の存在しない江戸時代の人が車を欲しいと思わないと同じように、
「できた経験がない」「できることを知らない」ことについて、
「やりたい」とは思えないものです。
そのような場合は、
もっと経験を積ませてできることを増やさせることが必要になってきます。
そういうことも問題を切り分ける目があるから考えることができます。
次回は例題を使って練習をしてみましょう。
(つづく)
このように、自分の仕事の進め方や置かれた環境を振り返り、
力を発揮するために必要なことを考えることを
「ダブルループ学習」と言います。
「ダブルループ学習」について解説をした『ひとつ上の思考力』 好評発売中です。